自作小説『足音』
これは、フィクションです。
ですが、これを読むことにより何かしらの恐怖体験等に遭遇したとしても、当方は一切の責任を負いません。
それでも読む場合は、どうぞ
『足音』
クラスメイトの伊達くんから相談されたのは、三ヶ月前のことだった。
「あのさ、話があるんだけどいいかな?」
同じクラスではあったが、特に仲が良いという訳でもない伊達くんから話し掛けて来た時、もしかしてという予感がした。
その当時、怪談や幽霊などが、ちょっとしたマイブームで、色々と体験談などを聞きまわったりしていた。
そのせいもあってか、この手の相談が、たまにやってきたのだ。
伊達くんの話をまとめると次のようなものだった。
伊達くんが、その存在を感じ始めたのは、一年も前のことだった。
ある日、一人、風呂場で頭を洗っていると後ろに何かの気配を感じた。
急ぎ後ろを振り向いたが、そこには何も居なかったという。
その次の日も後ろに気配を感じたが、やはり後ろに何かを見つけることは出来なかった。
それが十日ほど続いた後だろうか。
風呂場以外でも目を閉じていると何かの気配が背中に付きまとうようになった。
それは、最初、気のせいと思えるような小さな気配だったのだが、二ヶ月もすると、その気配は、どんどん強く感じるようになっていった。
それでも、自分に気のせいと言い聞かせて、強がることが出来た。
その気配というのは、遠く後ろから、じっと見られているといったものだったという。
四ヶ月目あたりから、気配に混じって、微かに音が聞こえるようになってきた。
最初、単なる耳鳴りかと思っていたが、やがてそれが、何か意味のある音に聞こえてきた。
それは遠くから忍び寄るような足音だったという。
それでも、音も気のせいだと言い聞かせようと頑張ったという。
僕が知る限り、その頃から、陽気だった伊達くんが、口数が減り、いつも眠そうな顔をして、一人でいる事が多くなっていった気がする。
伊達くんが言うには、その頃から、目を閉じるのを、眠りにつくのを恐れ、夜中でも目を開いて、明け方にやっと疲労と眠気から短い睡眠を貪る日々が続いていたのだという。
だが、伊達くんのそんな努力空しく、音は次第にはっきり聞こえるようになり、気配も相変わらず感じ続けていた。
そして、僕に相談をしてきた前の日、とうとう目を閉じた真っ暗なマブタの向こうに何かが見えるようになったのだという。
僕は最初、怪談、幽霊好きを公言してる僕をからかいに来ているのかと思っていた。
だけど、伊達くんの話しを聞く内に彼が真剣であることが伝わってきた。
僕は、その当時、知識として知っていた簡単なお払いを幾つか教えた。
その代わり、毎日、状況を教えてくれる事を約束した。
次の日、伊達くんに話しを聞いたところ、少しは、お払いが効いているようだとのことだった。
正直は話し、僕自身、教えたお払いが効果を発揮したことに少なからず驚いていたのを覚えている。
それから少し経ち、伊達くんは学校を休みがちになった。
夏休みを目前として、たまたま伊達くんが学校に来ている時、最近の様子を聞く事が出来た。
伊達くんに声を掛けた時、驚いたのが、以前より生気を失い落ち窪んでいるのに、ギラギラと見開かれている瞳にだった。
声も前とは別人のように掠れ、変わっていた。
そして伊達くんから聞いた最近の様子は次のようなものだった。
お払いを始めるようになってすぐに親が不信がるようになったのだという。
最初は、親を無視していたのだが、ついに耐えられなくなり、洗いざらい話すことにしたのだそうだ。
ところが、親は信じる所か、騙されているとか、頭がおかしくなったと言い出したのだという。
その日以来、親とは言い争いが続いているのだという。
最近では、精神科医に行かされたり、お払いの邪魔をしようとすることもあるのだという。
そして最後にこう言っていた。
「今でも目を閉じると、そこに居るんだ。
そこに居て、ずーっと待っているんだ…」
それから、伊達くんは学校に一度も来ることなく、学校は夏休みへと入っていった。
そして、夏休みもちょうど真ん中に差し掛かった日の夜。
伊達くんから僕の携帯にメールが送られてきた。
「ごめん」
それだけの文章が、打ち込まれていた。
その夜、こちらから何度か電話とメールを送ったが、伊達くんが電話に出ることも、返信メールが送られて来る事もなかった。
夏休みが明け早々、クラスでは席替えがあった。
席替えの終わった座席表には、伊達くんの席が、どこにもなくなっていた。
伊達くんと前仲の良かった人の一人が、伊達くんはどうしたのかを先生に聞いた。
先生は、ただ「家庭の事情によるものだ」とだけ言って、目を合わせようとはしてくれなかった。
僕は、もう伊達くんと会うことは無いだろうということだけは、理解した。
そして、事実、それ以来、僕が伊達くんと会うことはなかった。
著作権について
当作品の著作権は全て著者が有しています。
当作品の無断転載・二次利用を禁止します。

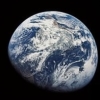
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません